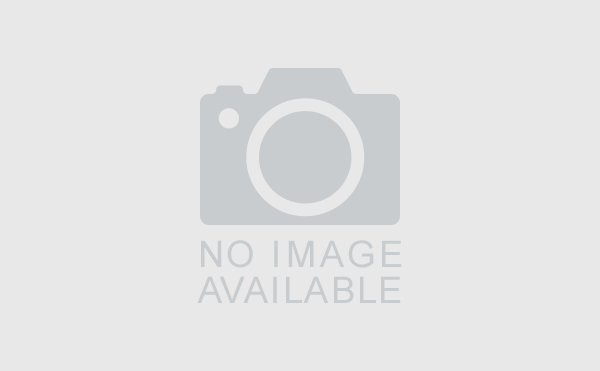琉球 第二尚氏王統の起源と概要
今日は琉球王国の歴史の中でも特に興味深い「第二尚氏王統」について、簡単にわかりやすくお話しします。
琉球王国のルーツは源為朝にあった⁉
琉球の王家の起源は、なんと日本の武士・源為朝(みなもとのためとも)にさかのぼります。
源為朝は平安時代、保元の乱で敗れて伊豆に流される途中、嵐に遭い船が琉球の今帰仁(なきじん)に漂着しました。そこで地元の有力者、大里按司(おおざとあじ)の妹と結婚し、息子「尊敦(そんとん)」をもうけました。
尊敦は成長後、浦添按司となり、若くして琉球の王「舜天王(しゅんてんおう)」に推されます。これが琉球王国の第二尚氏の始まりとされています。
第二尚氏王統の誕生
尊敦の子孫たちは代々王位を継承し、時代を経て1415年ごろに尚円王(しょうえんおう)が現れます。尚円王は第二尚氏の祖として知られ、琉球王国の強力な統治者として名を馳せました。
この尚氏の系譜は、30代以上にわたり歴史の中で続き、琉球王国の政治・文化を支えました。
琉球王国と日本のつながり
興味深いのは、琉球の王統が日本の皇室や武士の流れと深く結びついていることです。清和天皇の血筋に連なる源為朝の子孫が琉球の王となったという話は、琉球の正統性を示す大切な物語として受け継がれてきました。
また1609年には薩摩藩の支配下に入りましたが、それでも第二尚氏の王たちは琉球の文化や政治を守り続けました。
琉球 第二尚氏王統 簡略系図
鎮西八郎 源為朝(1138-?)
↓
尊敦(舜天王)(1166-1237)
└初代中山王、元浦添按司
↓
順熈(舜馬王)(1185-1248)
↓
義本王(第3代)(1206-1260)
↓
浦添王子 尊義 羽地按司 某(1236-?)
↓ ↓
金武按司 朝 羽地按司 北山王 怕尼芝(1290-1352)
↓ ↓
伊平屋大主 伊平屋大主
↓ ↓
伊平屋里主 第2尚氏王統祖 尚稷(没1434)
↓
尚円王(1415-1476)
├尚徳王(尚円の子)
├阿武加那志(娘)
└法茂志多礼眞加戸金(娘)
↓
尚眞王(1465-1527)
├浦添王子 朝満(1494-1540)
│ ├浦添王子 朝喬(1512-1576)
│ │ └尚懿(没1584)
│ │ └尚寧王(1564-1620)
│ └佐敷王子 朝雄
├大里王子 朝榮
├今帰仁王子 朝典
├越来王子 朝福
├尚清王(1497-1555)
│ └尚禎、尚元(1528-1572)
├金武王子 享仁
└豊見城王子 源道
↓
尚寧王(1564-1620)
├勝連按司 朝久
├勝連按司 朝綱
├浦添親方 朝師
├尚康伯
├尚豊(1590-1640)
├尚盛
├尚樞
├尚亨
├尚是寶
└尚全矩(早世)
↓
薩摩藩支配下(1609年)
↓
浦添王子 朝良 中城王子 朝益
↓
尚恭 尚文 尚賢(1625-1647) 尚質(1629-1668)
↓
尚貞(1645-1709)
├大里王子 朝亮
├名護王子 朝元
├北谷王子 朝愛
├東風平王子 朝春
├本部王子 朝平
└宜野湾王子 朝義
↓
尚純(1660-1707)
├豊見城王子 朝良
├小禄王子 朝奇
└美里王子 朝禎
↓
尚益(1678-1712)
├野國王子 朝直
└越来王子 朝得
↓
尚敬(1700-1752)
└読谷山王子 朝憲
↓
尚穆(1739-1794)
├中城王子 哲(1759-1788)
├浦添王子 図
├勝連王子 周
├尚容
├尚恪
├聞得大君 加那志(女子)
└複数の娘
↓
尚温(1784-1802) 夭折
↓
尚育(1813-1847)
↓
尚成(1800-1803)
↓
尚泰(1843-1901)
├宜野湾王子 朝廣
├尚興
├尚順(1873-1945)
├尚秀
├尚光
└尚時
↓
尚典(1864-1920)
↓
尚昌(1888-1923)
↓
尚裕(1918-1996)海軍大尉
↓
尚衛
簡単な説明
-
源為朝が日本から琉球に漂着し、琉球豪族の娘と結婚して尊敦を生む。
-
尊敦は浦添按司となり、功績で中山王となり「舜天王」となる。
-
その子孫が琉球第二尚氏王統の始まりで、尚稷から王朝が本格化。
-
尚円王、尚清王、尚寧王など歴代王が続く。
-
1609年薩摩藩の支配が始まるも、尚氏は琉球王国の王として続く。
-
明治時代以降も尚氏の子孫は存続し、最後の王、尚裕まで続く。
まとめ
-
琉球第二尚氏の王統は、源為朝から始まる歴史的な系譜。
-
尊敦が琉球で舜天王となり、そこから続く王家の流れが尚円王らによって確立された。
-
琉球王国は日本との深い歴史的関係を持ちながら独自の文化を育んだ。
-
現代に至るまで、この系図は琉球の歴史とアイデンティティを語る重要な資料となっている。