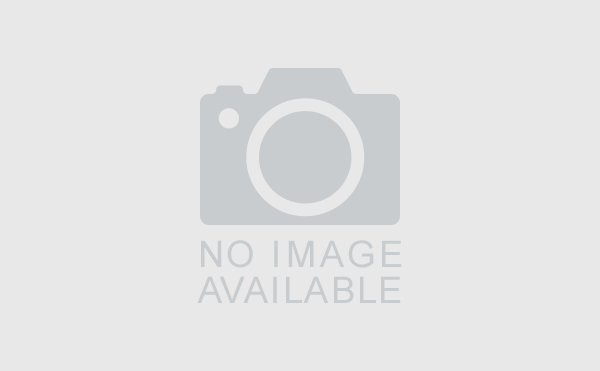【歴史を受け継ぐ人々】義村朝明
【歴史を受け継ぐ人々】義村朝明、琉球の魂を守ろうとした頑固な政治家
今日は、私のひいおじいちゃん・義村朝義の父、義村朝明(三世義村按司朝明)という人物について書きます。
あまり知られていませんが、彼は琉球王国の歴史の転換期を駆け抜けた、非常に重要な人物です。
その名は、家譜と村史の中にひっそりと残されていますが、今こそ改めて彼の生き方を記録し、語り継ぐ時ではないかと感じています。
義村御殿の三世 ― 向志禮・義村按司朝明(ちょうめい)
朝明は1830年(道光10年/天保元年)、首里に生まれました。彼の生まれた義村御殿(よしむらうどぅん)は、第二尚氏王統から枝分かれした名門家系で、王族の血を引く一族です。
朝明の幼少期、そして青年期を彩ったのは、琉球王国の衰退と激動の時代。特に、1879年(明治12年)の琉球処分(廃藩・廃琉置県)は、彼の人生を大きく変える出来事となりました。
「琉球魂」を背負い立った指導者
明治政府による琉球併合に対し、朝明は強く反対しました。彼は保守派=頑固党(がんことう)の中心人物として行動し、国王尚泰が東京へ連行されたあとも、琉球の独立を諦めませんでした。
東風平間切(現・八重瀬町)の地頭として、当時疲弊していた地域の復興にも奔走し、農村の再生、民衆の暮らしの立て直しに尽力した人物でもあります。彼の村史に描かれた姿は、まさに陣頭指揮に立つリーダーそのもの。「東風平魂」を象徴する存在だったのです。
清国への亡命と、最期
やがて朝明は、長男の朝眞(ちょうしん)とともに、清国へ亡命。日本に奪われた琉球の独立を、清国に訴え続けました。
しかし、清国は日清戦争で敗北。頼みの綱が絶たれた中で、朝明は独立運動の最後の頑固党首領として福州の地で客死。その志半ばでこの世を去りました。
息子の朝眞もまた、父と同じく福州で客死。親子そろって祖国の土を踏むことは叶いませんでした。
息子・朝義による「帰郷」の物語
時は流れ、1933年(昭和8年)。四世・義村朝義(ちょうぎ)は神戸から福州へ渡り、亡き父・朝明と兄・朝眞の遺骨を洗骨し、沖縄・平良の本墓へと改葬しました。
福州で客死してから35年の歳月。この間、家族が手を尽くしてようやく二人は祖先たちの眠る土地へと還ることができたのです。
義村朝明の評価
義村朝明は、単なる王族の一人ではありません。彼は滅びゆく王国の魂を背負い、最後まで「琉球人」であろうとした政治家であり、父親であり、そして闘志でした。
日本と清、二つの大国の狭間で翻弄されながらも、国家と村と家族を守ろうとした彼の姿は、もっと多くの人に知られるべきだと思います。
最後に
私にとって、義村朝明はただの「先祖」ではありません。彼の生き方には、小さな島国の中で誇りと責任を持ち、理想を貫いた一人の人間の物語があります。
現代の私たちが失いかけている「志」という言葉。彼の人生には、それが確かにあったのだと、今、声を大にして言いたいです。