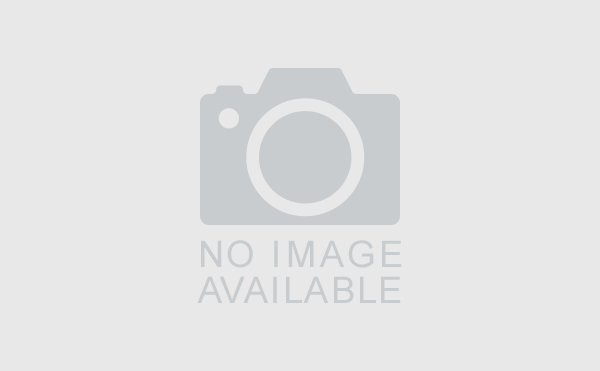私のヒおじいちゃん、義村朝義について

今日は私の家族の中でも特別な存在ヒおじいちゃん(曽祖父)義村朝義について書いてみたいと思います。
義村朝義(1866–1945)は、琉球王国の王族の血を引き、書道、絵画、空手に精通した多才な人物でした。
私にとっては歴史の中の偉人ではなく、家系の中に実在した「おじいちゃん」の一人。
けれどその人生は、まるで映画のように波瀾万丈です。
子どもの頃に空手を学び始め、松村宗棍や東恩納寛量といった名だたる師匠に師事。
馬術にも秀で、後に家督を継いで商売を興すなど、時代の荒波の中で力強く生き抜いた人でした。
終戦の年、大阪空襲の中でその生涯を終えましたが、晩年は書画や三味線などの文化を愛し、芸術家としての側面も色濃く残しています。
1979年には、遺族から彼の書画が沖縄県立博物館に寄贈され、1981年には「義村朝義展」も開かれました。
 |
 |
義村朝義(1866–1945)の詳しい簡単な説明
出自と家柄
義村朝義は1866年(慶応2年)、琉球王国の名門・義村御殿(よしむらうどぅん)の家に生まれました。父は義村按司朝明、母は伊江王子朝直の娘で、王族の血を引く名家の次男でした。義村御殿は尚穆王の三男を祖とし、東風平間切(くちんだまぎり)(現・沖縄県八重瀬町)を領地としていました。
幼少期と武術の修行
首里の広い御殿で育ち、使用人に囲まれ自由奔放に育ったといいます。11~12歳ごろから空手を学び始め、最初は家臣からナイファンチやパッサイの型を学びました。17~18歳からは、首里手の大家・松村宗棍に師事し、五十四歩、クーサンクー、棒術、剣術などを習得しました。その後、那覇手の東恩納寛量にも学び、「サンシン(サンチンの誤記か)」「ペッチウリン」などを修めました。
その他の修行
10歳から馬術も学び、19歳から23歳までは名馬術師・真喜屋に師事。屋敷内の木馬で型を練習し、実際の馬場でも訓練しました。
家督と事業
1897年(明治30年)、父と兄が清国へ亡命したため家督を継ぎました。1898年には明治政府から家禄(家臣としての給与)を止められたため、生計を立てるために事業を始めます。中国茶の輸入商を皮切りに、1904年にはパナマ帽子の製造会社も設立しました。一時は成功したものの、事業は次第に衰退しました。
晩年と文化活動
晩年は東京や大阪で暮らし、書道・絵画・空手・三味線などに親しむ文化人として過ごしました。1945年(昭和20年)3月14日、大阪空襲で死去。享年80歳。
没後の評価
1979年、遺族から約50点の書画作品が沖縄県立博物館に寄贈されました。1981年には同館で「義村朝義展」が開催され、彼の芸術的・文化的功績が再評価されました。